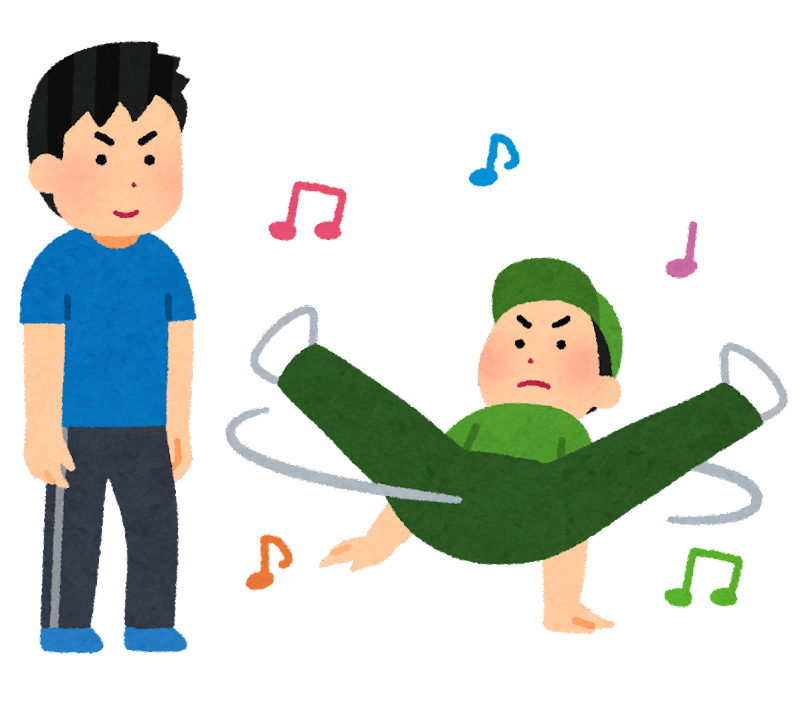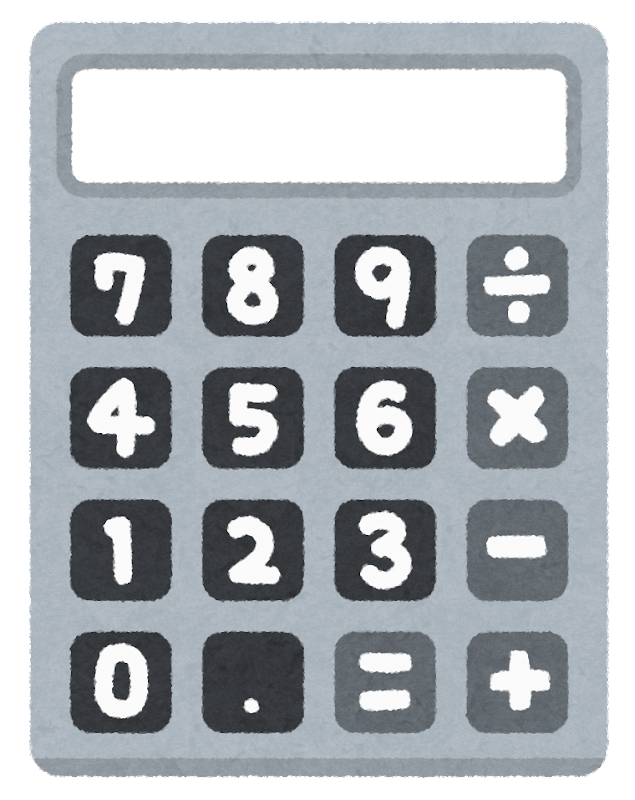おはようございます。
塾長の鈴木です。
早いもので、もう11月ですね。
さて、4字熟語で、
「因果応報」という言葉があります。
現代の一般的な使われ方では、良い行いをすれば、良い行いが返ってきて、悪い行いをすれば、悪い行いが返ってくるというところでしょうか。
しかし、これは明らかに成り立ちません。
本来の意味は、恐らく、因果というのは、私は「自分の想い」ではないかと思います。
例えば、誰かに嫌がらせをされる人は、周りに嫌がらせをしている人かといえば、別にそうとは限らないでしょう。
嫌がらせを受ける人というのは、「嫌がらせを受けたくない」と強く不安に目を向ける人です。
つまり、因果は自分にあるのですが、それは、周りへの「行動」ではなく、「想い」だということです。
因果応報の本当の語源等は知りませんが、恐らく、この言葉が生まれた時には、「心」や「想い」の部分だったかと思います。
それが、現代になり、「目に見えるもの」ばかりに焦点をあてることで、意味が変わってしまったように思います。
もし、現代の意味で使われるような「因果応報」などが成り立つのであれば、世の中恨みつらみばかりのゆがんだ世の中になるでしょう。
嫌な思いをする人がいれば、「あいつはもっと嫌な目に合うはずだ」のような。
これは、やはりおかしいです。